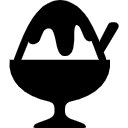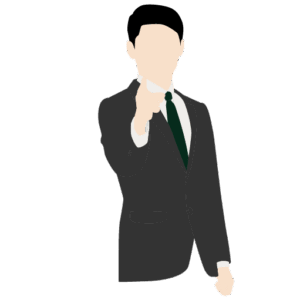ストレスチェック結果の返却/セルフチェックをしよう

皆さんこんにちは☀
ストレスチェックへのご協力ありがとうございました。
個人結果の返却は8月末に送付する予定となっています。
結果が手元に届きましたら以下のことに注目してみてください。
🔹 結果の見方(セルフチェック)
多くのストレスチェックでは、以下のようなカテゴリで評価されます:
- ストレス要因
仕事の量・質、職場の人間関係、コントロール感など - 心身のストレス反応
疲労感、不安、抑うつ、イライラなど - 周囲のサポート
上司・同僚・家族からの支援があるかどうか
🔸 結果の判定:代表的な分類(例)
カテゴリ 状態
ストレス反応が高い 高ストレス状態の可能性
サポートが低い 周囲からの支援が乏しい
仕事の負担が高い 業務過多または役割不明瞭
総合判定:高ストレス者 医師面談の対象になる可能性
✅ ストレスチェックを「実施しただけでは意味がない」主な理由
① 高ストレス者への対応がなければ意味がない
高ストレスと判定されても、医師面談の申出がなかったり、会社側が対応を怠るとリスク放置になる。
面談を受けても、その後の職場環境の調整(配置転換や業務負荷の見直し)がなければ改善につながらない。
② 集団分析を活用しないと組織改善に役立たない
実施後の「集団分析」(部署ごとのストレス傾向の可視化)を行わない、または見ても何もしない企業が多い。
職場単位の課題(例:上司の対応、業務負荷、人間関係など)に気づいても何も変えなければ、根本的な問題は放置されたまま。
③ 継続的な対策がなければ一過性のイベントになる
年1回のチェックだけでは、継続的なメンタルヘルス対策にはつながらない。
長期的に働きやすい職場環境を作るには、定期的なフォローアップや再評価が不可欠。
④ 労働者の信頼を損ねる可能性
「実施しただけで放置」「形だけやって終わり」という印象を与えると、従業員の信頼を失う。
次回以降のチェックで正直に回答されなくなる、医師面談を希望しづらくなるなど、形骸化のリスクがある。
⑤ 法律上の義務を果たすだけで終わってしまう
ストレスチェック制度は、「メンタルヘルス不調の未然防止」が目的。
単に「実施義務を果たした」という最低限の法令対応にとどまっていると、実質的な意味はない。
🔎 具体的な改善アクションが必要
実施内容 実効性を高めるポイント
高ストレス者の抽出 医師面談を促し、本人の希望に沿った対応を実施する
集団分析 結果をもとに職場単位の課題を明確化・改善提案を行う
フォローアップ 1年ごとだけでなく、定期的な確認と再評価を行う
教育・研修 管理職・従業員に対するメンタルヘルス教育を実施する
🔚 結論:「測って終わり」は意味がない
ストレスチェックは、「チェック(測定)」よりも「その後の対応」こそが本質です。
実施した結果をもとに、職場の風通しや働きやすさを改善し、メンタル不調を予防することが制度の目的です。
社内全体としての結果はまた10月に開示させていただきます😊
産業医面談を希望するかたは是非管理本部まで連絡ください。
健康経営ページへ戻る