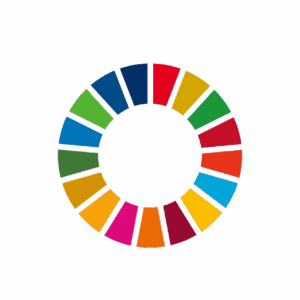猿払村のホタテ事業に学ぶ ―「すべてを賭けて育てた成功モデル」
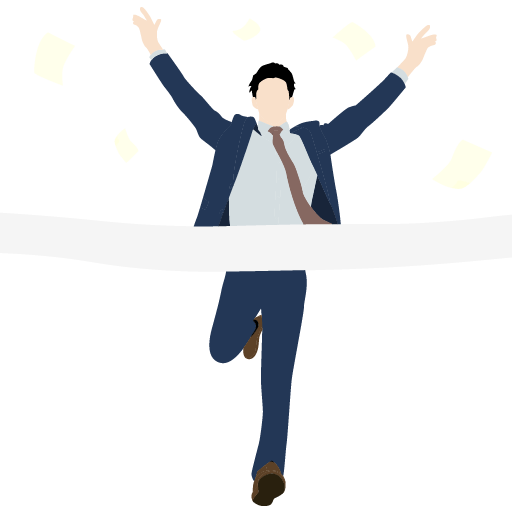
北海道最北の猿払村は、かつて炭鉱の閉山と漁業不振で疲弊し、「日本一貧しい村」と呼ばれていました。
昭和39年にはホタテ資源がほぼ枯渇し、将来像を描けない時期が続きます。
転機は1960年代後半。当時の村長・笠井勝雄氏と漁協組合長・太田金一氏が「村の未来をホタテに懸ける」と決断し、村は当時の年間税収の半分強を稚貝購入に充てるという大胆な方針を採りました。
1971(昭和46)年、村と漁協は稚貝の大規模放流と漁場造成を開始。ここから再生が始まります。
猿払の本質は「すぐに獲らず、育てて獲る」。
稚貝放流・天敵駆除・サイズ選別などの資源管理を、村・漁協・漁業者が一体で徹底。
4年貝の品質を磨き、加工・ブランド化で付加価値を高め、貝殻再利用など環境との共生にも踏み出しました。
結果、日本一のホタテ水揚げで知られる産地へ。数字以上に、持続可能な仕組みが地域に根づいたことが価値です。
この成功の裏には、“最初にリスクを取る勇気”があります。村長らの覚悟が共通目標を生み、組織と地域を動かしました。
私たちの仕事にも同じ教訓があります。
現状維持に甘えず、資源・人・信頼を育てる長期視点で、仲間と挑戦すること。
猿払の物語は、「勇気ある決断が未来を拓く」ことを教えてくれます。